―WONDER MAKER―(第二章)
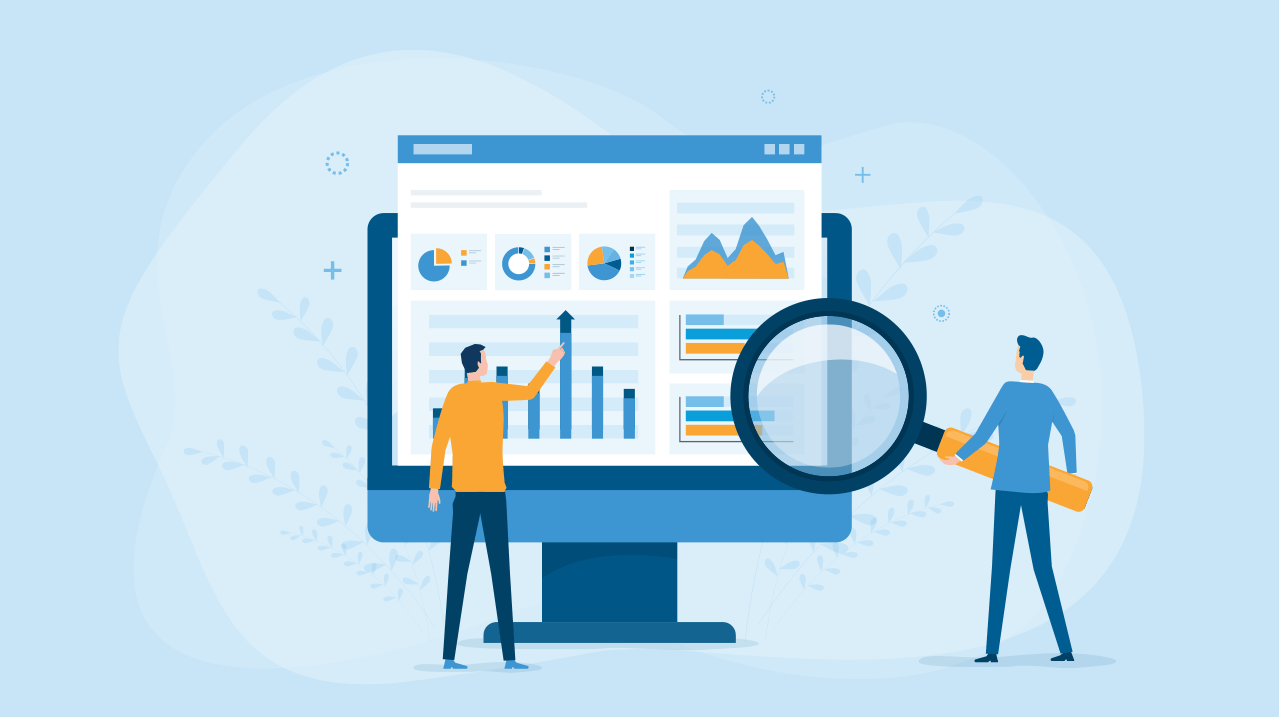
第二章 異世界転生者のサムライ⁉ 謎の剣士・オノダ見参。
ドランクタウンでのダニエル様ハンマー投げ事件から一夜明け……。
ここは隣町『フリーデン・ファウンテン』。
桃色&橙色に色めく木々と古い女神像の噴水広場が有名な、とても閑静で裕福な住宅街。
昨日の一件で私の働く酒場『コルクの家』は店全体がボロボロの状態となり、女店主のリンダおばさんがひどく気を病んでしまったことで今は一時休業中。
しばらく暇を出された私は、数ヶ月前から始めた夜の中心街のクラブでの仕事まで時間、気ままにこの町を散歩をしていたのですが……。
『嬢ちゃん……可愛いね?』
「え……あのぉ」
『その可愛さならきっとすぐナンバーワン行けちゃうよ? ねえねえ、ウチに来ない?』
噴水広場近くの道ばたで、おひげのカールした怪しげなおじ様に変な勧誘を受けてしまいました。
わたし、こういうの苦手なんだけどなぁ……。
すると、一人の女性が近寄ってきて怪しげなおじ様にこう言ったのです。
「この子、私の恋人なんですけど?」
「ええっ⁉」
『そ、それは……大変失礼致しました……っ!』
怪しげなおじ様はそそくさとその場を後にし、彼の姿が見えなくなった辺りで私はその女性にお礼をしたのです。
「た、助けて下さってありがとうございましたっ」
「あなた、人に話しかけられやすいでしょ」
「? ええ、まあ」
「でしょうね。だって隙があるから」
なんだか素っ気ない態度でそう言うと、女性もその場を立ち去ろうとしました。
「……」
しかし私はこの時、心に思い浮かんだことをついポロッと口に出してしまったのです。
「……ロミオさん?」
「……マジかよ」
その言葉を口にした女性の声は、間違いなくロミオさんの声でした。
ロミオさんはその日、何故か〝女装〟をしていたのです……。
それからは女神像の噴水の縁に座りながらロミオさんと世間話を少々。
「ふぅ……それで? お前なんで俺だって気づいたんだ?」
「私、昔から人よりも五感が鋭いみたいで……人の声とか、匂いとか、仕草とか、すぐに分かるんです」
「声真似も変装も演技も完璧だったはずだが……?」
「はい、そう思います。でも、なんとなくロミオさんのような気がして……」
「お前すげえな」
ロミオさんは女装したまま胡座を掻き、近くの店で買ってきたホットドッグを頬張りながら感心した様子でそう言いました。
「てかさ、あの酒場にいた……ゴードン? とかいう強面のおっさんちゃんと生きてた?」
「ええ、無事でした。少し気を失ってはいたみたいですが……」
「そっか。まあ花火野郎より弱いんじゃ、偽物なのは確定だな。次会ったら謝らないとなぁ……」
「絶対に謝った方がいいと思いますよ?」
ここで私はふと、昨日から疑問に感じていたことを聞いてみることにしました。
「そういえば、ロミオさんが人違いしていた相手の方ってこの島の住人なんですか?」
「ん、本物の方か? 違うよ?」
「そうですか……」
「いやあ、昨日は昼間っからヤケ酒しててさ。探してる男が全然見つからなすぎて、多分焦ってたんだろうな。あのおっさんが〝怪力のブルース〟ってヤツに見えちまったんだよ」
「たしかに、『あの男を倒すためにこの島に来た』って言ってましたね」
「ああ、そいつな……」
ロミオさんは腰のポーチから一枚の手配書を取り出して、私の目の前に突き出しました。
「この男の居場所について何か知ってるか?」
『 《WANTED》
NAME:アダム
ALIAS:〝絶望〟
BOUNTY:200,000,000SHELL
REMARKS:重要情報提供募集中。討伐は魔法族ギルドにお任せを』
「全然知らないです……。それよりも――」
「どうした?」
「――これって『魔法族ギルドの討伐案件』ですよね?」
「うん、そうだけど」
「そうだけど……って、なんであなたが倒そうとしてるんですか⁉ ロミオさんって人間族で、しかも単独の賞金稼ぎですよね⁉」
「人間族で単独の賞金稼ぎが追っちゃいけないとは書いてないじゃん」
「当たり前すぎて書いてないだけですっ!」
「『討伐は魔法族ギルドにお任せを』ってことは、別に任せなくてもいいってことだろ?」
「えぇ……?」
常識が通じないのは昨日の時点で分かってたけど。
この人……やっぱり超がつくほどのマイペースで、しかもド天然だ……。
「まあ心配されたのは今回が初めてじゃないよ。でも、もう俺決めたんだ」
「決めたって、何をです?」
「……この男だけは、必ず俺がぶっ倒す!」
そう宣言したロミオさんの紅玉色の瞳に、平時の野心と……何かその他の感情の色が混ざっている気がしたのは私の思い込みなのかもしれないけれど。
少なくとも、昨日出会ったばかりのロミオさんの人物像を伝説じみた噂の中でしか聞いたことがない私には、きっと踏み込んではならない領域の話。
それに。
ロミオさんには、昨日からどこか火薬のような匂いを感じるのです。
今日まで危ない世界で生きてきたのは、賞金稼ぎという肩書きからも想像に難くありませんが……。
話題を変えた方がいいかな。
すると、ロミオさんの方から次の話題を振ってきてくれました。
「お前も海外からきたんだろ?」
「あっ、はい。……そうですね、ロストガールです」
「ネバーランドの魔法族って割と有名なヤツ多いよな。なんだっけ、名前……?」
「私の名前ですか? メルと申します」
「お前のじゃねえよwww」
【エスプル・ハルディン】
ネバーランドを拠点とする魔法族ギルド。
魔法族全体の中での勢力としては〝中級〟らしいのですが、世界的に有名な魔法族が多数在籍していることで知られています。
彼らは現在、戦国時代の熾烈な争いにはほとんど参加していないものの、海外の並み居る強豪たちから見ても決して無視ができない凄い存在なのだそう。
「俺でも知ってるのは……銀世界、月光、賢人ネロ……この辺りかな」
「その三人は有名なので私も知ってはいますけど……そもそも魔法族についてあまり詳しくないので、彼らの本当の凄さは分からないです」
「ん……簡単な話だぞ? つまり魔法族ってのは『四系統の魔法使いの総称』だよ」
ロミオさんの話をまとめると……。
魔法族と呼ばれる人類は、その中でも四つの区分がされているとのことでした。
魔法石の力を使って戦う……異能戦士。
神々から神器を授かった……神官。
現世の精霊と契約を結ぶ……精霊術士。
高度な魔導学知識を持つ……魔導師。
ちなみに彼曰く……これらの四つの魔法使いの中でも特に強力なのは、異能戦士。
魔法族の説明を終える頃には、ロミオさんはホットドッグをすっかり完食していました。
「ちなみに今、ギルドの本部とかにいけばそいつらに会えたりするのか?」
「いえ……彼らは今ネバーランドにはいません」
「え、なんで?」
「数週間前から天空島に行っているんです。精鋭のシュバリエが全員同行する程の最重要の任務だとかで……」
「はあ……? ってことは……ギルドの主力全員が今はこの島にいないってことか⁉」
「そ、そういうことになりますね……」
「平和ボケするにも程があるだろ……もしヤバいのが海外から来たら終わりじゃん」
私がじっとロミオさんを見つめると。
「何見てんだよ。俺別にヤバくねえよ」
(自覚ないんだ……)
「?」
ロミオさんの頭の上に疑問符が浮かんでいるように見えました。
「……でも何か引っかかるよな。島の住人全員の命より優先される程度の任務なんだろ?」
「私が酒場でお客さんから聞いた噂によると……なんでも、とても重要な積み荷を運んでいたとか」
「積み荷か……。〝絶望〟とは流石に関係なさそうだな」
「あ、そういえば……一人だけ残ってました! とっても偉いお方が!」
私はこのタイミングで、まだ島に残っているその人物の存在を思い出しました。
「おっ、誰だ⁉」
「ソフィア様です! 【エスプル・ハルディン】の君主を務めているお方!」
「ネバーランドの王様ってことか!」
ソフィア・ワンダーガーデン。異名は〝夢幻〟。
代々ネバーランドを治めてきた『ワンダーガーデン家』の現当主にして、魔法族ギルド【エスプル・ハルディン】の君主……つまり、全てのシュバリエの頂点に立つ女性です。
私はまだ彼女を間近で見たことはありませんが、その姿はまるで〝妖精のお姫様〟のように美しく、歴代の当主の中でも最高峰に位置する強力な精霊術士だと専らの評判……。
その上で数年前、天空島にある魔法学院『ノブレスオブリージュ』を創設以来トップの成績で卒業した超才女……とてつもなく聡明な頭脳の持ち主でした。
「へえ~! てことはめっちゃ強くて権力あるってことか! オマケに超美人!」
私からソフィア様の情報を少しだけ聞いたロミオさんは、思わず鼻の下を伸ばします。どうやらソフィア様への妄想を頭の中で色々と膨らませているみたい……。
しかし。
そんなロミオさんもすぐに正気に戻りました。
ここまでの話の流れにおいて一つだけ、明確に残されたある疑問に気がついたようです。
「ん、ちょっと待てよ? そんなに偉くて強いなら何でそいつだけこの島に残ったんだ?」
「はい……それにはきちんとした理由が存在します」
数日前に海外からやってきたロミオさんが知っていたネバーランドの魔法族の三人。
〝銀世界〟ハーヴァ・ヒルデブラント。
〝月光〟セリス・トワイライト。
〝賢人ネロ〟ネロ・ワンダーガーデン。
世界的に有名なこの三人の中には…………やはりソフィア様は含まれていませんでした。
「――メル、教えてくれ。……ソフィアってこの島でどういう立ち位置なんだ?」
「……ソフィア様は――」
しばし間を置いて、私はその真実を語ったのです。
「――――このネバーランド一番の〝嫌われ者〟です」
「〝嫌われ者〟……? この島の王様なんだろ? 尊敬されてないってことか?」
「いえ、そうではありません」
「じゃあ、なんで嫌われてんだよ」
「ネバーランドの……〝裏の王族〟に逆らったからです」
「〝裏の王族〟……?」
「彼らの意思に逆らうシュバリエや住人たちは、この島ではまず生きてはいけません」
「その話……もしかして昨日の花火野郎も関係あったりするのか?」
私は、静かに頷きました。
ネバーランドという島国には、表と裏の二つの顔が存在していました。
まずは、表の顔。
それは世界的にも平和で有名な騎士の国。
魔法族は気品に溢れ、島の住人たちからも大いに尊敬を集める理想国家。
そして、裏の顔は……。
「私のようなロストガール……この島にいるロストボーイたちは皆、オズワルド様によって〝奴隷〟として集められた人たちなんです」
「自分たちの意思で逃げてきたんだろ?」
「その通りです。ただ……私たちはこの島に来る前、〝平和〟という言葉の意味を大きく勘違いしていました」
「……」
この島国にロストボーイを集め始めた人物……。
その人物の名は、オズワルド・ヒルデブラント。
〝裏の王族〟と称される程の絶大な権力を有する『ヒルデブラント家』の現当主にして、ネバーランド貴族の元締めである男性でした。
二十年前に世界が戦国時代に突入した頃、彼は〝表の王族〟『ワンダーガーデン家』の弱みを握り、貴族社会を味方につけ、ネバーランドの実権を握った後……『ネバーランドの繁栄』と『世界の混乱』を結びつけて一つのアイデアを思いつきました。
それが――。
「つまり……オズワルドって黒幕が戦国時代に〝平和〟を求める弱者を島にかき集めて自分のビジネスの労働力として死ぬほどコキ使ってると……?」
「はい……」
「……賢いな」
「えっ?」
「それで、あの花火野郎の家も所詮は『ヒルデブラント家』の一子分に過ぎなかったと?」
「レオパルド家はヒルデブラント家の側近の家系の一つです。ダニエルさんの父親のガンドロフ・レオパルド卿はオズワルド様と長年の友人関係……縁が深いのは確かでしょう」
「ズブズブの関係ってワケだな」
「逃げること、戦わないこと……それによってもたらされた平和に自由なんてなかった。私たちは結局、甘い誘惑に釣られただけの、ただの大馬鹿者です」
「ふーん……」
タン、タン、タン。とロミオさんは貧乏揺すりをしながら、私にこんな質問をしました。
「……で、ソフィアがそのオズワルドに逆らったってのは、いつの話だ?」
「魔法学院を卒業して帰国した直後……ワンダーガーデン家当主就任の式典の演説中です」
「その演説で何か、オズワルドにとって都合が悪いことを言った……?」
「はい」
「ソフィアは一体、何を言ったんだ?」
あの日のソフィア様の言葉は、今でも忘れられない。
私は一語一句違わず、彼女の演説の最後の台詞を口にしました。
「『私は必ず、この戦国時代を終わらせてみせる』……と」
「……本気か?」
「ええ。オズワルド様が発言の撤回を強く求めたそうですが、ソフィア様は一切応じなかったそうです」
「ほ~ん……」
「ただ、その発言は今では完全になかったことにされているようです。あの演説の内容を蒸し返した者は、後日ギルドからひどい制裁を受ける羽目になるのだとか……」
「まあ、当然そうなるよな。『戦国時代の平和』を最大の売り文句にしてるのに、それを真っ向から否定されたワケだし」
「最初の質問の答え……主力の中でソフィア様だけが島に残っている理由ですが、それは彼女が今も完全にギルドから孤立しているからです」
「傀儡の王様にすらならないから、政治&軍事からも完全に干されたってことか……。その様子じゃあ監視役もついてるだろうし、今世界で起きてる〝勢力争い〟に参加することも不可能……『戦国時代を終わらせる』なんて夢のまた夢だな」
「シュバリエが島の住人の多くから人気を集める反面、ソフィア様は島の平和と秩序を乱そうとした〝破滅の魔女〟として疎まれていますし……難しいと思います」
それでも……私はソフィア様のことを心から尊敬しています。
生まれながらに才能に恵まれた、美しく聡明な彼女が言ったその言葉は……きっと冗談でも妄言でもないと思うから……。
きっと何か深いお考えがあるはずだと、今でもそう信じているのです。
私がそこまで話し終わると、ロミオさんは噴水の縁から立ち上がって、ぐーんと伸びをしました。
「おしっ、そろそろ変装調査を再開するか……。色々教えてくれてありがとな!」
「いえ、こちらこそ助けて頂いてありがとうございました!」
「ああ、そうだ。今からまた別の町に行きたいんだけど、どこか人の多いトコ知ってる?」
「人が多いトコ……ですか」
私がパッと思い当たったいくつかの候補地の提案をして……。
そこでまた色々と会話があった後に……まだ仕事まで時間がある私は、道案内をしながらロミオさんと途中まで一緒に歩くことになりました。
ザッ、ザッ……。
スタ、スタ……。
(……?)
彼と歩き出した直後から……私は妙な胸騒ぎを覚え始めます。
なんだか今日は、これ以上ロミオさんと一緒にいない方がいいような……?
そんなおかしな予感をかき消すように、私はロミオさんに昨日の話題を再度振ります。
「ところで……ロミオさんって、本物の〝英雄〟なんですよね?」
「おう、本物だぞ!」
「昨日は本当に驚いちゃいました。まさか筋肉の力で魔法族を倒していたなんて……!」
「おう、『筋肉は全てを解決する』からな!」
「私……皆のために戦える強い人って素敵だと思います」
「お……ん?」
「これからも賞金稼ぎの活動、頑張って下さい。……危険な職業だと思いますが、私も影ながらあなたの無事を――」
「何言ってんの?」
「へ?」
「――俺、今追ってるヤツ倒したら賞金稼ぎ辞めるぞ?」
「……え?」
あれ……?
私――また何か勘違いしてる?
「まさか、こんな命懸けで危ない仕事を俺が好き好んでやってるとでも思ったのか……?」
「あ……あの、えっ?」
「はぁぁぁぁ……」
「ご、ごめんな、さい……」
ロミオさんは限りなく低いトーンで、深い溜息を吐いた後。
ひどく呆れた表情で私を見て……明らかに軽蔑の視線を送りながらこう言い放ちます。
「俺はな……一度たりとも人前で〝英雄〟なんて名乗った覚えはないんだよ」
ここからのロミオさんはまるで、ずっと心の中に溜まっていた不満を一気に爆発させるように……動揺する私の様子に構うことなく数々の言葉の矢を放ってきたのでした。
「軟弱で臆病なお前ら〝弱者〟が俺のことをどこでどう思っていようが勝手だけどさ……理想のヒーロー像を勝手に押し付けくんなよ」
「大体、人助けなんてくだらないエゴだぜ? そんなこと進んでやるヤツってのは、助けたら助けた人数だけ相手から自立の機会を奪ってんだ。ただの〝自由の敵〟だよ」
「ソフィアが部下の三人よりも影が薄い理由は分かった。だがさっきの話聞いてて、俺はオズワルドって男の方が賢くて正しいと思った。そもそも……実現不可能な理想論者なんかに誰もついてかないのは当然だろ?」
「ろくに実力もないヤツが一丁前に〝愛〟だの〝平和〟だのと言ってるのを見ると吐き気がしてくる。『俺ですら無理なのに、お前ら如きに世界を変えられるワケないだろ』ってぶん殴ってやりたくなるわ……フルパワー状態の筋肉でな」
次々と持論を展開していくロミオさんの姿が、少しずつダニエルさんの姿に重なって見えてきた私――。
昨日まであれほど嫌っていたダニエルさんの記憶が、だんだんとロミオさんに塗り替えられていく。
これは完全に私のミスだ。
私が勝手に舞い上がって、本人の望まない未来を願い……ロミオさんを怒らせた。
『心配されたのは今回が初めてじゃない』。
彼はさっき、手配書を私に見せた後にそう言っていた。
きっと、身の危険の心配だけじゃなくて自分をヒーローに仕立て上げようとする人たちの無責任な期待も受け続けて、この三年間ずっとストレスを抱えて生きてきたんだろうな。
「ごめんなさい。あなたの気持ちも考えずに、軽率な発言をしてしまいました」
「……別にいいよ。なんか、俺も色々ぶちまけすぎたわ。悪い」
空気が重い……。
でもここから他の話題を出す気にもなれず、今さら道案内を下りることもできず。
モヤモヤとした気分のまま分かれ道を目指し、ただひたすらに町の中を歩き続けるしかありませんでした。
とても気まずい私たちが無言で歩き続けてから、数分経った頃。
ザワザワ……。
「道が……」
「完全に塞がれてるな」
私たちの前方には、昨日のドランクタウン以上の人だかりができていました。
道の端から端まで町の住人でぎゅうぎゅうに埋め尽くされていて……なんとか掻き分けて進めるような、そんな隙間も無いほどに。
「とりあえず、ここは諦めて迂回するか」
「ええ……」
『はなせっ! このっ!』
『! おいっ、このクソガキ! 暴れるなっ!』
「……!」
「ん? おい、どうしたメル」
『たあっ!』
『おわっ、危ねぇ! こいつ刃物もってやがった!』
「……あの子の声だ」
「はあ? ……って、おい何するつもりだ!」
私は急いでその声の主を確認しようと、人だかりの最後尾から住人たちの頭の隙間を探し出そうと右往左往……。
そして、道の左側の一ヶ所だけ……道の向こう側が少しだけ見える位置を見つけました。
(っ! やっぱりあの子だ!)
その子は、昨日のドランクタウンでロミオさんに出会う前に酒場の路地裏で店の残り物を囲んでいた貧しい子供の中の一人……。
喉に南瓜を詰まらせて、私が背中を叩いてあげた『食い意地の張った男の子』でした。
男の子の近くにはシュバリエが三人……おそらく男性二人に女性一人。
『大人を舐めんのもいい加減にしろっ、この万引き小僧がっ!』
バキッ!
『ぐあぁっ!』
「ああっ!」
男の子はシュバリエの男性に顔を蹴り飛ばされ、地面に倒れ込んでしまいました。
(どうしよう……この状況だと下手したら殺されちゃうかも! とにかく助けないと!)
ダニエルさんに本当に殺されてしまったあの万引き犯の男性の最期の姿が思い浮かび、慌てた私は無理矢理にでも体を人だかりの中にねじ込もうと試みるのですが……。
『ちょっ、アンタ邪魔っ!』
『押すなゴラァ!』
「ごめんなさい! どうしても通りたいんです!」
『チッ、ロストガールかよ! ……よそ者風情が図々しいわ!』
人だかりの後方にいた成人男性が、拳を振り上げてから私の顔目掛けて――。
「きゃ!」
パシッ。
『⁉』
思わず閉じてしまった目を開けると……ロミオさんが男性の拳を止めてくれていました。
「あんた今……この女のこと、思いっ切り殴ろうとしたな?」
『なんだよお前……ペッ!』
「……」
その男性は地面に唾を吐くと、どこかへと去って行き……。
「あ……ありがとうございま――」
カラン……コロン……。
――私がロミオさんにお礼を言いかけたその時、初めて聞くような不思議な音がどこからか響いてきたのです。
「?」
「ん、なんだこの音…………靴音か?」
カラン……コロン……。
ロミオさんがふと横を見ると。
「――失礼仕る」
「ああ……」
その剣士の方は不思議な靴音に反応したロミオさんを一瞥してから、人だかりの中に強引に割り込んでいってしまいました。
『ちょっ……何なのこの人――――んんっ?』
『痛っ、腰の剣当たってるんだけど――――んんっ?』
それまでぎゅうぎゅうに詰まっていた人たちは彼の異質な風貌を確認するやいなや、身をよじらせて通り抜ける隙間を作っていきます。
結果、剣士の方はスルスルと人だかりを通り抜け……そして。
カラン……。
男の子と三人のシュバリエの前でピタリと立ち止まりました。
剣士の方はとても珍妙な出で立ちをしていて……。
顔立ちはとても凜々しいけど、どこか厳か。瞳は琥珀色。
キリッとした整った黒い眉毛に女性のように長い黒髪のポニーテール。
腰に差された二本の剣は、鞘も、柄も、全部真っ白。
〝異国風〟の茶色い上服に、足元まで伸びた長いスカート(?)。
そして不思議な音の鳴る靴は足の甲が開いた木の板のような変わった形状でした。
剣士の方はまず……男の子にゲンコツを一発。
ゴチンッ!
『いでっ……!』
『『えええ⁉』』
シュバリエ三人組も、流石にこの展開には仰天した様子。
それから男の子の刃物をスッと取り上げてから……今度は、彼ら三人の方を向いてこんな台詞を言ったのです。
「……見苦しい」
『見苦しい? ……それって、オレたちのことかよ』
「自覚ありか」
『なんだって……?』
「まだこの地がどこかも分からぬが、妙なことに言葉は通じるようだ。余所者の拙者が他国の道理に口を挟む資格はないが……言葉を交わせるというのなら、言わせてもらおう」
剣士の方は周囲をぐるりと見渡してから、こう続けます。
「公衆の面前で平然と童を甚振り、ゲンコツ一つで済む仕置きに無用な刻を費やす……。貴殿らには他に為すべきことはないのか?」
『そのガキはココじゃ有名な万引き常習犯で、その上人に切りかかったんだ。ガキだろうが立派な罪人、裁き方はオレたちの自由――』
「フン……己らを童と同列に語るというのか。大人が聞いて呆れる……」
『偉そうに。さっきからアンタ、誰に聞いてるか分かってんの……?』
「この地の兵と見受けるが……何か?」
『オレらシュバリエには、業務妨害の罪でお前を処罰する権限だってあるんだぞ?』
「ほう……ではその後、上の者にはなんと申すつもりか? 『暴れる童一人に手間取り、その最中邪魔者が入り処罰をした』と?」
『それがどうした?』
「貴様らは相当な〝弱卒〟のようでござるな。……その気ならばお相手致すが、如何?」
『分かったぜ……。望み通り、ここでぶっ殺してやるっクソ剣士!』
(昨日に続いてまた戦いが……。もしかして昨日からこの島――――どこかから悪い気でも集まってきてるのかな……?)
とりあえず男の子に大きなケガはなさそうなのは良かったのですが……。
会話の内容を聞いていると双方共にとても血の気の多い方々のようです。
しまいには、私の隣にいたロミオさんが何故か不気味な笑みを浮かべながら、こんなことを言い始める始末……。
「――あいつ、俺と同類かもな」
「トラブルメーカー、ってことですか……?」
「さっき一瞬アイツと目が合ったんだ」
「?」
「あれはただの剣士の目つきじゃねえな。超一流の賞金稼ぎとして色んなヤバいのと対峙してきた俺の経験上、あんな目をしてるのはせいぜい百戦錬磨の賞金稼ぎか傭兵くらいだ。あとは――」
「――平気で人を殺せる〝殺人鬼〟……あたりかな?」
「え⁉」
「まあ、あれだ。善悪関係なく『人殺し』には資質があるってことさ」
「ロミオさんも……平気で人を殺せるんですか?」
「うん。だって生きるか死ぬかの世界だし、賞金稼ぎって」
「あ……そう、ですね」
きっとそんな資質は、私には全然ないんだろうな。
包丁で指を切っただけでも気を失いそうになるくらい、血が苦手ですから……。
私はこの会話をロミオさんとした後、剣士の方の一挙手一投足から片時も目を離せなくなってしまいました。
すると、さっきまで普通だったはずのシュバリエの方々がいきなり円陣を組み始め……。
『オリバー!』
『マーク!』
『デイジー!』
『『〝月光〟セリス・トワイライト様の新米親衛隊〝月下三人組〟、ラジャーッ!』』
「……何をふざけている」
『『フザけてねえよ!』』
なんとなく気合いが空回りしてるような……新米ってことは新人シュバリエなのかな?
「うっわ、弱そ~。コイツら見るからに三下キャラじゃん,誰の前座だよwww」
「ちょ……ロミオさん失礼ですよ!」
この後に誰か強い人が出てくるみたいな言い方、本当に辞めて下さい。ロミオさん。
『炭酸水〟』
オリバーさんは泡の水流をシュワ~ッと両手から吹き出し……。
『〝魔人〟』
マークさんはポケットからウネウネと赤い魔人を出し……。
『〝跳兎〟』
デイジーさんはとにかくピョ~ンと高く飛び上がった……。
「……!」
剣士の方は襲いかかってくる三人の様子に目を細めながらも、腰の剣に手を添えて――。
「あれ……?」
「まあ……この実力差じゃ剣を抜くまでもないよな」
剣士の人は剣を鞘に入れたまま腰から引っこ抜き、前方にスッに構えると。
そのまま音もなく颯爽と走り出し……。
なんと三人をすれ違いざまに、剣の先端の金具で急所を的確に突いていったのです!
ドドドッ!
『『おぉぉ……っ!』』
彼らは喉仏や鳩尾を押さえながら悶絶し、立ち上がれずに戦意を喪失してしまいました。
「フッ……まだまだ青二才よ」
剣士の方は、まだ新人で若い三人の醜態を見て、やや楽しげな表情で笑います。
こんな感じの表情をする方を、私も酒場で働いている時に何度か見た記憶がありました。
経験不足な若人が焦る姿を見て、冷やかしを言ってみたり揶揄ったりするような……。
「若くば意地で向かってこい。さあ、いつまでうずくまってる。……さっさと立てい!」
彼は剣の鞘で、オリバーさんの頭をポカッと叩きながら喝を入れます。
『ぐぅぅ……っ!』
「軟弱な男に何が守れるっ! ほら、立てぃ!」
多分この方も、ロミオさんとは別の意味で〝変人〟なのでしょう……。
……ボコッ!
それは――。
剣士の方が熱血な眼差しと口調で〝月下三人組〟の方々を叱っていた、その最中に起きた突然の出来事でした。
ワー、ギャー……ワー、ギャー……。
「あの剣士、説教長えな……。おいメル、さっさと他の道に……って、うわあっ!」
「? ロミオさん、どうかしましたか?」
「じ……じじじじ地面から、な、なななな『生首』、がっ……」
「え、そんなハズは――――きゃああっ!」
ロミオさん曰く〝殺人鬼〟かも知れないその剣士の方から少しだけ目を離して彼の視線の方向を見てみると……私の立っていた場所の一メートルほど後ろの地面に、その生首はありました。
「メメメメメメメメメメメメm」
「おおおおおお落ち着いてくださいロミオさん! ちゃんと喋って!」
「落ち着けるかあっ! いきなり生首だぞ⁉ オバケかもしれないんだぞ⁉」
※あとで本人から聞いた話によると、ロミオさんは『オバケはもう死んでるクセに突然出てくるから、意味不明すぎてNG』なのだそうです。生きてる人の血は全然大丈夫らしいのに、本当に不思議ですね。
その生首は……ウェーブした茶髪の、オールバックの壮年男性でした。
目は閉じているけれど、彫りが深い造形の顔立ちで、頬にはそばかすがあって……。
あれ、どこかで見覚えのあるような?
でも……あまり直視していると、なんだか突然目が開いたりなんかしそ――――。
ギョロ!
「「ぎゃあああああああああああああああっっ‼」」
思わずロミオさんと私は、互いの体を力強く抱きしめ合ってしまいました!
今の彼の肉体は外からは一見華奢に見えるのに、抱き合った感触は意外と逞しくて……。
じゃなかった。
ぎゃあああああああああああああああっっ‼
「――フンッ!」
ボゴゴゴゴゴゴッ……!
「あ、あれ……生きてる?」
生首の方はあっさりと地面から全身を出し、パンッ、パンッ、と高価そうな素敵な衣服を叩きます。
「ビックリした……一瞬オバケかと思った!」
その人が存命だと分かった途端、ロミオさんは安堵の表情を浮かべます。
「アンタ……いや――――まあ大変っ、大丈夫ですか? お怪我はございませんか?」
「⁉」
そういえば一連の流れで忘れてたけど……ロミオさんって今女装中だっけ。
完全に女性の声だ。さっき声真似って言ってたけど、一体誰の声を真似してるんだろう?
そんな女装姿のロミオさんが彼の衣服に付いた土を一緒に払おうと手を伸ばすと……。
バシッ!
「触れるな……白豚風情が」
「――あ? ……今なんつった、お前?」
一瞬にして空気がピリつき始めました。
生首の方は、身の毛もよだつほどの激しい憎悪と軽蔑に満ちた目つきでロミオさんのことを睨みつけます。
しかし……その方はすぐに視線を人だかりに移し、それから彼は前を向いて歩き始めました。
「……なんだアイツ。クッソ偉そうな態度だな」
露骨に不機嫌になるロミオさん。
昨日の酒場でのあなたの振る舞いも大概だった気がしますが……。
でも確かに……初対面であの呼び方は普通の人の感覚じゃあり得ないような。
「どけ」
『あん? 何だおま……って、ええええええええええええええええええええええ⁉』
『? なにいきなり……って、わあああああああああああああああああああああ‼』
生首の方を見た人だがりの人々は皆、次々と大声で叫びだし……。
それから――――あっという間に彼の目の前には『一本道』ができあがり……人だかりを作っていた住人たちは、その一本道の両脇で深々と頭を垂れていました。
『『ガ……ガンドロフ様っ⁉』』
うずくまっていたシュバリエの三人は、生首の方の姿を見ると、サササッ! とすぐさま立ち上がって敬礼をします。
「ガンドロフ? あれ、そいつって確か花火野郎の――って、メル。お前何やって……」
「……頭を下げてください、ロミオさん」
私は今、周りの人たちと合わせて深々とその生首の方に頭を下げることにします。
「? いやだ」
この人はもう……!
――私は今日、初めて自分が暮らす町の領主の顔を知りました。
生首の方の正体は、ネバーランド西岸一帯を治める大領主『ガンドロフ・レオパルド卿』です。
昨日ドランクタウンでロミオさんが投げ飛ばしてしまったあのダニエルさんの父親……。
「……?」
剣士の方はガンドロフ卿を見ますが……至って平然。彼の立場を全く知らない様子です。「フム……」
カツン……カツン……。
ガンドロフ卿は茶色の顎ひげを撫でながら、目の前の一本道をゆったりとしたペースで歩いて行きます。
すると、シュバリエの一人……デイジーさんが彼に状況説明をしました。
『がっ……ガンドロフ様っ、我らは現在〝月下三人組〟は万引き常習犯のロストボーイの少年と、業務妨害を行ったこの剣士を処罰している最中であります!』
「デイジーよ」
『はいっ! 何でしょうっ、ガンドロフ様!』
「……君は今日も可愛いな」
『え……』
ガンドロフ卿からの突然の褒め言葉にデイジーさんは、ボッ! と顔を赤くして……。
『そ……そんな、私なんか……可愛くなんて、えへへへ……!』
『相変わらず惚れっぽいのな、デイジー……』
「オリバー、マーク。お前たちもご苦労だったな。まだ新人なのに事件対応とは、なかなか精が出るじゃないか。よく頑張った……下がって良いぞ」
『『! はっ、はいっ! お褒めに預かり恐悦至極にございますっ! これからも精一杯頑張らせて頂きますっ! 失礼致しましたっ!』』
オリバーさん&マークさんも、大貴族のガンドロフ卿に褒められ頬の筋肉が緩んでいる様子……。
そして彼らはすたこらさっさと、その場を走り去っていきました。
「さて」
それから、ガンドロフ卿は男の子の前に仁王立ちして――。
『おじさん……だれ?』
「……」
すると。
ガバッ!
『⁉』
次の瞬間、ガンドロフ卿は…………男の子の体を力強く抱きしめたのでした。
「……えっ?」
「チッ」
今、ロミオさんが静かに舌打ちをした気が……。
その時私は、激しい違和感と共に……一種の気味の悪さを覚えました。
この感情は……『悍ましさ』とでも言うのでしょうか?
先ほどのロミオさんに対するあの態度……『白豚風情』……。
一本道が出来上がる前に微かに聞こえた……『どけ』と口にしたときの低い声のトーン。
なんなのだろう、この人……。
私のセンサーが緊急発令でこう伝えている。
『男の子が、危ない』。
動かなければ――動け、私。
そう思った私は、速やかにその場から足を動かした。
……がしかし、何故かロミオさんが私の体を制止して――。
『く、くるしいよ……おじさん』
「君は……ロストボーイの子供だね?」
『そ、そうだけど』
「お母さんは生きているかい?」
『……しんじゃったよ。たべるものがぜんぜんなくて! おまえたちのせいだ!』
「――すまなかった」
『え……』
「君たち家族を不幸にしたのは、この私だ……! 万引きをしてしまう程に追い詰めてられていたとは……。領地領民の生活をしっかりと見てこなかった、自分が恥ずかしい……」
ガンドロフ卿は涙ぐんだ瞳で男の子の肩を抱き、彼の目を見ながらこう言った。
「償いをさせてくれ……。もう、君たち家族に二度と辛い思いはさせないから」
『おじさん……』
「メル、このウィッグちょっと持ってろ」
「え……はい、分かりました。ちゃんと持ってます……!」
ふんっ! と鼻を鳴らしたロミオさんが女性服を着たまま元の髪に戻り、ボキボキと首や肩を鳴らしながらガンドロフ卿の方へと向かっていく……。
「この金貨をあげよう。今まで一生懸命に生き抜いた君への、おじさんからの〝勲章〟だ。……貰ってくれるね?」
『うん……っ、もらう……っ!』
小さな目からポロポロと涙をこぼす男の子。剣士の方は無表情で微動だにしない。
「よしよし……さあ、家族の元にお帰り。お父さんによろしく伝えてくれたまえ」
『わかった! 金貨ありがとうねっ! バイバイ、おじさんっ!』
「うん」
男の子が踵を返しながらガンドロフ卿に満面の笑顔で手を振っている。
にこやかに別れる二人……なわけない!
ガンドロフ卿は胸元からスッと拳銃を取り出し、
パァン!
……容赦なく男の子の背中に向けて発砲した。
でも。
『『……っ⁉』』
「……!」
そんなこと、弱い私にだって予想できた未来。
つまり……ロミオさんと、そして――――男の子を身を挺した庇った剣士の方がそれを防げないわけはないのであった。
じわ……。
剣士の方の左肩の袖の布が少しずつ変色していく……。
「っ……貴様ッ!」
「フゥゥゥ……ひどいな。短くも悲惨だった蛆虫の一生、最期くらいは幸せな勘違いで締め括ってあげようと思ったのだが……やはり肉と分かり合うのは流石に無理があったな」
ガンドロフ卿……否、ガンドロフは。
そのウェーブした茶髪をくしゃくしゃと掻き毟りながら、はっきりとそんな言葉を言った。
「私は精霊術士。万が一にも化けて出てこられちゃあ溜まったもんじゃないからねぇ……」
「先の言葉はどうした……よもや、端から守るつもりもない契りと交わしたと申すかッ!」
ガンドロフは拳銃の引き金の穴に人差し指を通し、クルクルと回しながら応える。
「そこをどけ異邦人。私は今からソレを殺し……ギルドに死体を持ち帰り、私の城の前で磔にした後、父親を探し出さねばならない」
「探してどうする……我が子の死体を見せるつもりか?」
「処刑するさ、見つけ次第すぐにだ。それから……父親も死体の横で親子仲良く磔だ。子の罪は親の責任だろう?」
『い、いやだよっ……こわいよぉおおおっ! うわああああああああああんっ!』
男の子はその言葉のあまりの恐ろしさに、剣士の方にしがみついて大声で泣き叫ぶ。
こんな子供相手に、なんて残酷な想像をさせるのだろう。
絶対に、絶対に、許せない。
そんなの、私が絶対に止めてみせる――どんな手を使ってでも。
剣士の方のおかげで再び揉め事の中心にならずに済んだロミオさんも、ガンドロフへの怒りで眼光が鋭くなっているように見えた。
「あんのクソジジイが……花火野郎の方がまだマシだな」
「ええ……!」
すると、剣士の方がいきり立ち、ガンドロフの目を真っ直ぐな瞳で見つめながら告げる。
「拙者、貴様のような〝力ある外道〟が大嫌いにござる……!」
「ほう……?」
「貴様の名は知らぬが、兵や民たちに敬われる立場であるようだ。ならば、己の守るべき存在になぜ手をかける……? しかもあのような食うにも貧しき童を裏切ってまで……!」
「――〝人の言葉を喋る肉〟だ」
「肉……だと?」
「そうだとも。我ら魔法族のため、領主である私のため……人間族、ロストボーイは生き続けるのだ。力ある存在に利用され、搾取され、奪われ……最後には命まるごと食われるための肉として飼い殺しだ。このネバーランドという『檻』の中で一生な……」
「……どこまで人を虚仮にする気だ!」
「これが〝真理〟だ」
ヒュゥゥゥゥゥ……。
その場に静かに風が吹いた。
剣士の方が、ついに名を明かす。
「拙者は流浪人、名は小野田総治郎と申す。所詮は余所者、もはや交わす言葉もない。故に……これより一人の〝剣客〟として貴様に決闘を申し込まん!」
オノダ……さん? とても変わった名前……。
それから剣士の方……オノダさんはゆっくりと、滑らかな動きでスーッと剣を抜いた。腰に差した二本の剣の長い方の剣だった。
「得物は『般若』。白塗太刀拵、乱刃丁子……。この刀と脇差『天狐』は――」
「――剣士を六道の輪廻より外す……〝妖刀〟にござる」
「何を言ってるのか分からんわ」
ガンドロフには、オノダさんの言っている言葉の意味が分からなかったようだ。
まあ……私にも分からないけれど。
「私の名も教えようか。どのみち、お前は犯罪者……蛆虫親子共々、処刑対象だ」
ガンドロフ・レオパルド
異名:〝土竜〟
セーブポイント数:二〇〇
魔法:陸の幻霊・ベヒモス
「ロミオさん、あの人……ガンドロフは元ギルドの主力《アルカディア》の一人です」
《アルカディア》。
現在天空島に滞在している精鋭のシュバリエたち全員の総称だ。
魔法族ギルド【エスプル・ハルディン】の主力集団であり、ネバーランドに三万人いるシュバリエたちの中でも、選りすぐりの四十人が集められている。
今は引退しているものの、ガンドロフはかつてその内の一人であった。
「私は普段天空島にいるが、今はたまたま帰ってきていてね……そしてそんなタイミングで、つい昨日息子がどこぞの賞金稼ぎとやらに大怪我を負わせられた」
「ギクッ」
ロミオさんの体がぎこちなく固まる。
そういえば……ロミオさんが〝女装〟してた理由ってもしかして?
「素行不良で反抗期、いつまで経っても大人貴族になりきれないモラトリアムの馬鹿息子。だが……それでも愛しの我が子だ。今現在ギルド本部で〝英雄〟とやらの手配書が作られているが、トドメは私が刺せるよう文言を付けておいた。必ず私の手で息の根を止めたい」
「……ヒュ~、ヒュ~♪」
「ロミオさん……ウィッグ返しますね?」
「お、おう……」
ロミオさんはやっと現実逃避を辞めて、再び大人しくウィッグを付けたのだった。
「子の罪は親の罪と言ったか。……ならば、親を見て子は育つもの。拙者に子はおらんが、馬鹿息子などと宣うならば貴様が正道に立ち返らせよ!」
「見たところ三十路のようだが、その歳で子も持たない非モテがこの私に講釈を垂れるな。……そもそも息子は馬鹿だが、それ以前に私に似て美しく才能のある自慢の我が子だ。今はダメでも私の地盤と看板を継いでいずれはこの――」
何故か始まる子育て論争。
ダニエルさんの反抗期は、親馬鹿なこの人への抵抗意識もあったりするのかな?
「む、息子への愛は分かった……だが今は決闘の場、戦を前に情は禁物! いざ尋常に!」
「フッ……すでに戦いは始まっているが?」
「?」
ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ……。
『『な、何が始まるんだ……?』』
ガンドロフに道を開けて以降、静かに頭を垂れていた住人たちが周囲から鳴り響くその轟音に動揺し……そして。
――深い地の底から、それらはやってきた。
閑静な住宅街の美しい街並みに挟まれた私たちの立つ長い道路。
ガンドロフの不気味な笑い声と共に、道路に無数の穴が開き、その深淵から何かが這い出てくる……!
ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ……。
――〝暴食・大宴会〟。
穴の中から出て来たのは、ネバーランドの島の地下に住む伝説の巨大肉食モグラの群れ。
通称、『ネバーモウル』。
体長三メートル。真っ黒な毛に包まれており、大人の身長と同じ長さの巨大な爪を両手両足に五本も持っている。
ちなみに……クリクリとしたつぶらな目が意外と可愛い。でも確か鳴き声が……。
『『ヴィイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイッッピ!』』
『『うわああああああああああああああっ!』』
「うるさっ」
「これは〝威嚇〟ですっ! ネバーモウルはこの威嚇で地中の獲物を萎縮させて動きを鈍らせるそうですっ!」
「……お前詳しいな。モグラフェチなの?」
「……可愛い生き物とか綺麗な花のことは、昔から図鑑でよく見てたので……」
私たちはネバーモウルたちの威嚇音に耳を塞ぐのに精一杯。
しかし、オノダさんは全く動じることなく、体の右側に剣を縦にして構えている。
「妙な妖術使いの多いこと……やはり拙者は今〝天罰〟を受けているのだろうか……?」
「ムッフフフフ……魔法を見るのは初めてか?」
「否……訳あって今は拙者も妖刀使いの剣士。摩訶不思議にはもう慣れ申した」
シュウウウウウ……。
すると、オノダさんの剣からドライアイスのような白い冷気が発生し始め、物凄い勢いで周囲の空気が冷えていく……。
『『さ、寒い……っ』』
住人たちが次々と体を擦り始めた辺りで……私はこの後の展開に不安を覚え始める。
それは……。
「ん……寒っ!」
「あっ、待って……そんな! モグラたちが……っ!」
こんなことは、私の余計なエゴだって分かってるけれど。
オノダさんの冷気を発する剣が、これからモグラたちを斬り捨てることは明白だ。
「あれ全部、肉食のモグラなんだろ? そんなのに同情してたら住人死ぬぞ?」
「ネバーモウルが自ら地上に出てくることは滅多にありません! 目がほぼ見えないからです! それに……アレを見て下さい!」
「アレってなん……あ、あの茶色のやつか!」
ネバーモウルの黒い全身を、土色のオーラのようなものが覆っているのが見えた。
あれって、もしかしなくても魔法の力だよね?
「私の契約した『ベヒモス』は陸の王者……。ネバーランドの地下の全ては私の庭だよ。ベヒモスの力を使えば地中に眠るあらゆる貴重な鉱石も天然資源も取り放題。こんな巨大生物すらも私の〝奴隷〟として扱える……本当に最高の魔法だよ。ムッフフフフ!」
最低……っ!
自分の都合の為に、無関係なモグラたちを強引に戦いに巻き込むなんて……!
「純粋な息子にはまだ教えてないが〝真の貴族〟とは自らの手を血で穢さないものだ!」
『『ヴィイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイッッ‼』』
「……左様か」
「行けぃ!」
ガンドロフに操られたネバーモウルの群れが、一斉にオノダさんに襲いかかる。
――ちなみに精霊の話。
精霊には三つの階層が存在するようだ。
精霊、幻霊、神霊……。
それらは霊力の強さと格式によって決められ、階層が上がるごとに数は減っていくのだとか。
中でも強力なのは、火、水、風、土の四大精霊らしい。
オノダさんはスッと剣を抜き、それからくるりと刃を返してネバーモウルを迎え撃つ。
巨大な爪が幾度となくオノダさんに降りかかるが、彼は極めて滑らかな身のこなしで全てを躱し……。
ガガガガンッ!
『『ヴィィイイイ……!』』
……あっという間にネバーモウルを全頭峰打ちで気絶させたのだった!
「あの人、凄い……!」
内心ホッとしながらも、私はオノダさんの実力に圧倒されていた。
「チッ……使えないモグラ共め」
そう言うと、ガンドロフは両手をパンッ! と合わせ――。
――〝大震撼〟。
直後、地面がグラグラと激しく揺れ始める。
周囲の建物が波打ち、その場にいた住人たちは次々と転倒してゆく……。
「おっと、と、と……!」
「きゃっ!」
私とロミオさんもよろめいた後、二人同時に地面に尻餅をついてしまった。
しかし……。
「……フン」
オノダさんは全く動じることなく、平然とした態度で立ち続けている。
「大人しく転がっていればよいものを……」
ガンドロフが合掌をやめると、すぐに地震は収まった。
「先ほどから貴様は己の肉体で戦おうとせず、動物や妖術に頼ってばかり。もしや、己の実力に自信がないのか……?」
「……」
その台詞を聞いたガンドロフの表情がやや強ばる。
「いいだろう。私自らの手でお前を葬ってやる……ありがたく思え」
すると。
「ムフフフフ……」
醜悪な笑みを浮かべながら――ガンドロフはネバーモウルが彫った穴の中に飛び込んだ。
「……自殺か?」
しばし、その場に沈黙が訪れる……が。
――〝土竜の鉤爪〟。
「……!」
いち早く何かに気がついたオノダさんは、素早く真横に回避した。
ボコォォオオオオオオオオオン!
『『うわあああああ!』』
驚く住人たち。
それもその筈。なぜなら――鋭い鉤爪を装着したガンドロフが、オノダさんのいた足場から勢いよく飛び出したのだから!
「貴様……、また卑怯な手を……!」
「戦いにルールなど存在しない……!」
ムハハハハ! と高らかに笑うガンドロフ。
「せいぜい足元の見えない敵に怯えるがいい! 不安、恐怖、焦燥、そして絶望……。これら以上に美味なフルコースなどこの世に存在しない……!」
そしてガンドロフは再び地面の穴へと入っていく。
……その場に空いた全ての穴の深淵から、彼の悍ましい笑い声が地上へと響いてくる。
「まるで〝モグラ叩き〟だな」
「〝モグラ叩き〟……?」
ロミオさんの口から聞き覚えのない単語が出て来て、やや戸惑う私。
しかし、その言葉はすぐに分かった。
ガンドロフがあちこちの穴から現れる度に、オノダさんが剣を振る。
その繰り返しだ。
「ハァ……ハァ……」
オノダさんの息が少し上がってきたところで。
「さあ、どうする剣士よ……。このまま体力尽きるまで私と戦うか?」
「……」
「ロミオさん、あの人どうなるんでしょう……」
「まあ、なるようになるだろ」
あっけらかんと答えるロミオさん。
すると……。
「……? 何をしている」
オノダさんは突然剣を鞘に戻し、そして――両目をゆっくりと閉じるのだった。
「ふぅ……」
その様子を見たガンドロフの口角が少しずつ上がっていく。
「ムハハハ! ついに勝負を捨てたか。……だがもう遅い! 私も十分楽しめた。そろそろトドメを刺させて貰おう!」
ガンドロフは今度は自ら穴を掘り始め……。
ザクザクと凄まじい速度で鉤爪を動かして穴を掘り進め……深度が十、二十、三十……そして五十……百メートルに到達したところで、ガンドロフはピタリと停止した。
地上では、住人たちが不安げな表情で狼狽えている。
『ガンドロフ様……一体どこまで深く掘ってるんだ?』
『俺たちも危ない……皆逃げよう!』
わあああ……と。パニックに陥った住人たちが、遂にその場から逃げ始めた。
「ロミオさん、私たちも逃げましょう!」
「なんで?」
「ここに居たら危険です! あの子だって危ない!」
私は、まだオノダさんの近くで腰を抜かしている男の子に視線を移す。
しかし、ロミオさんは言う。
「逃げなくても大丈夫だ」
「⁉」
「ガンドロフは今、オノダしか狙ってねえから」
「……?」
まるでガンドロフの思考を読みきっているかのような口ぶりで、彼は確かにそう言った。
「〝心眼〟……」
オノダさんがそう呟く。
しかし、私はただ急いで男の子の元へと駆け寄るのだった。
地中では。
(ムフフフフ……これで終わりだ! 剣を抜くまでもなく串刺しにしてやる……!)
――〝土竜の冒険〟。
ギュルルル……と、ガンドロフはその場で高速回転すると、両腕に装着した鉤爪の先端を合わせて……。
彼の革靴に仕込まれたジェット装置が噴射されると共に――まるでロケットの如く地上へと急加速していく。
「早く逃げて!」
『あ……あぁ……』
腰を抜かして自力で立てない男の子に――。
「今、行くから!」
――私は叫ぶ。
「ムハハハハ!」
ガンドロフは笑う。
「……」
オノダさんは沈黙する。
「ったく……!」
ロミオさんは動き出す。
そして。
「ッッハァッッッッ‼」
ボッコォォオオオオオオオオオオオン!
地中から勢いよくドリルのように現れたガンドロフ……だが。
「⁉」
オノダさんは――地上にはいなかった。
つまり今、彼がいる場所は……。
「――御免ッ!」
ドカッ! っと、ガンドロフの首筋に峰打ちが入る。
「がはっ……!」
オノダさんがいたのは――ガンドロフの下だった。
バタリと、地面に倒れるガンドロフ。
『うえええん……こわかったよぅ……』
男の子は私の胸の中で泣きじゃくる。
「よかった……! 本当に無事でよかった……!」
男の子の涙につられて、私も泣いてしまった。
剣を鞘に納めながら、微笑むオノダさん。
私たちのすぐ側で、ふぅ、と溜息をつくロミオさん。
住人達が居なくなり、五人だけのその場に束の間の平穏が訪れる。
……本当に束の間だった。
『あ、いたぞ! あそこだ!』
『〝英雄〟もいるぞ! 必ず捕まえろ!』
「げ」
ロミオさんのウィッグは……地面に落ちていた。
多分、さっきの地震の時に頭からズレ落ちたのだろう。
「やっべー! おい、お前っ! さっさと逃げるぞ!」
「む……何故?」
「捕まったら死刑だぞ⁉」
「……受け入れよう」
「アホかっ! とにかく来い!」
ロミオさんはオノダさんの腕を引っ張りながら、その場から走り去っていってしまった……。
そして私と男の子と、気絶したガンドロフだけがぽつりと取り残されたのだった。
……ロミオさんといると、すぐに揉め事に遭っちゃうなぁ。
一方、中心街にあるギルド本部の最奥にある城。
その城の庭園の真ん中に座る一人の美しい少女が、花の香りに包まれながら蝶々と戯れていた。
「――ソフィア様。ご報告致します」
「……」
「昨日のダニエル様の一件に続き、フリーデン・ファウンテンでガンドロフ・レオパルド卿が別の剣士に敗れました」
「……そう」
少女……ソフィアは心底どうでもよさそうだ。
「その剣士は異国風の出で立ちをしており、海外から来たよそ者と思われます。現場にいた〝英雄〟と共に現在は逃走中であることから、賞金稼ぎロミオの仲間である可能性もあり……」
「――〝英雄〟」
「……ソフィア様?」
ソフィアはシュバリエの手を借りながら立ち上がる。
「なにか食べたい」
マイペースなソフィアに呆れるシュバリエ。
そのシュバリエの手には……ロミオとオノダ、二人の人相が描かれた手配書の束が握られていた。
夜になり。
ロミオとオノダはあれからシュバリエたちとの数時間にも及ぶ逃走劇の末、見事に逃げ切ったようだ。
「――つまり、お前はアエルの外から来た異世界人だと……?」
「左様」
「頭……イカレてんのか?」
「失敬なっ! 拙者は嘘偽りなど申しておらんぞ!」
「うぇ~、この人怪しい~……」
「何をぅ⁉」
堅物で、煽りや冗談を一々真に受けるオノダの反応を楽しむロミオ……。
「まあいいや。……てかさ」
「む……今度はなんぞ?」
ロミオはオノダの衣服を指差して。
「それって、ユカタか?」
「これは着流しだが……そなた、浴衣を知っているのか?」
「詳しくは知らねえよ? でも、確かどこかの国の民族衣装だったような……」
そんな会話をしながら歩いていると、前方から誰かがやってくる。
「――あっ」
「ん?」
メルだった。
「おお、メルじゃん。どうしたんだ? こんな夜中に一人で」
「こんばんは。これから仕事があって……」
「ふーん。まあ、夜道だし気ィつけろよ?」
ロミオはその時、メルの化粧の濃さから何かを察したようだが特に突っ込まなかった。
「はい。ありがとうございます」
続いて、メルが二人に質問を返す。
「お二人はこれからどちらへ?」
オノダがそれに答えて。
「我らはたった今、一泊の宿を探しているのだが……メル殿、どこか良いアテはござらぬか?」
「男性二人……一泊の宿……」
メルは二人を交互に見る。
「……いや違うぞ? 今日はもう疲れたし、明日島を出ようって考えてたとこで……」
その意味ありげな視線に、ロミオはブンブンと首を振った。
オノダがややロミオと距離を取る。
「何引いてんだお前、真に受けんな!」
先ほど揶揄われた仕返しのつもりだろうか……。
それから二言三言交わした後、ロミオたちはメルと別れる。
しかし、メルが立ち止まり……振り返って二人の背中を見て。
「ロミオさん! オノダさん!」
少しだけ声を張って、彼らを呼び止める。
「ん、なんだ?」
すぅっと息を吸って、それからメルは朗らかな笑顔でこう言ったのだった。
「私、二人に出会えてよかった!」
「!」
「……フッ」
その時のロミオの表情を見たオノダは静かに笑う。
「またっ……また来て下さいね! このネバーランドに!」
「……おう!」
やや素っ気ない態度でそう返事をしたロミオは、再び前を向いて歩き出した。
オノダもメルに軽く一礼した後、ロミオの後に続く。
「……また、会えたらいいな」
それから少しの間、二人の背中を見送るメルなのであった。
メルから教えて貰った宿に着いた二人は、入口付近でなにやらバタバタしているようだ。
「オノダ、これをつけろ」
そう言ったロミオがオノダに渡したのは、禿げ頭のカツラとつけヒゲであった。
「……これでよいのか?」
「ププッ」
「笑うなっ!」
オノダの衣服はこの島では目立つため、現在は夕方に(女装した)ロミオが買った黒いコートを羽織っている。
やっと二人が宿の扉を開けて中に入ろうとした……その時だった。
――。
「……ん?」
ロミオが立ち止まる。
「如何した、ロミオ」
「いや……なんでも――」
宿も向かいの建物と建物の間……真っ暗闇の路地裏に、その二人はいた。
――?
――。
その二人は、黒いローブにを包んでいた。
声からして……両方男だろうか?
ギロリ。
「!」
と、片方の男がこちらを見る。
ロミオはすぐさま目を逸らし……。
「……オノダ、さっさと入れ」
「ああ……」
その時のロミオの心臓は、これ以上無いほどにバクバクと音を鳴らしていた。
(なんだ、あの目は……! あれは人の目じゃねえ……〝魔獣〟の目だ……!)
その目を、ロミオは知っていた。
人生で二度目だ、あんな眼差しを向けられたのは。
確か最初は――。
「……!」
ロミオは意を決して、もう一度その人物を見た……が。
もうその路地裏には、誰も居なかった。
「――シャーロット……俺は戻ってきたぞ、この場所に。お前の作り上げた退屈な王国に」
「平和、秩序、理性、安定……。そんなもの、全部まやかしに過ぎない」
「教えてやるよ……人の本性。魔法族の真の在り方――〝本能〟と〝欲望〟が世界を支配した、あの時代の魔法族の生き様をじっくりとな……」
アダムは口ずさむ――。
――Das Marchen wird wahr.
「ネバーランドよ、あの女を恨め。……さあ、俺の描いた邪悪なおとぎ話を今始めようか」

